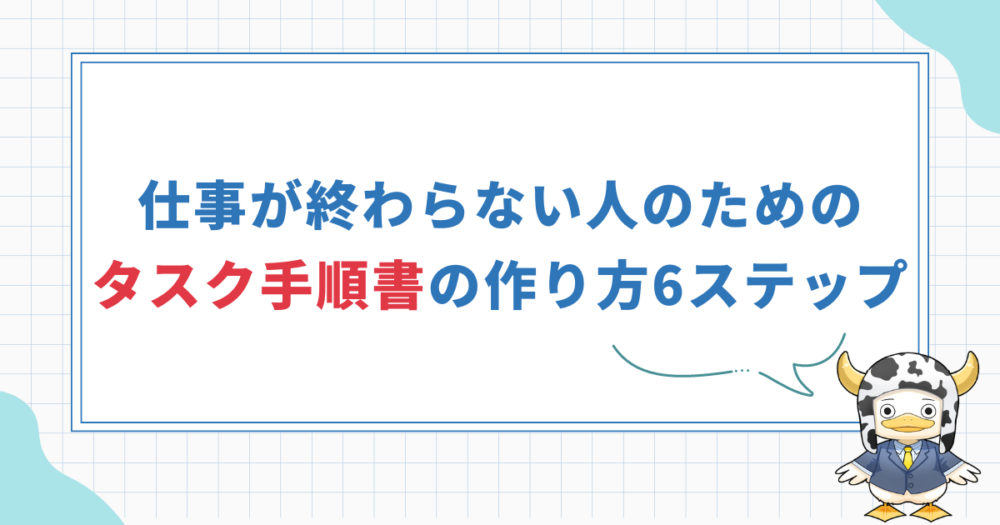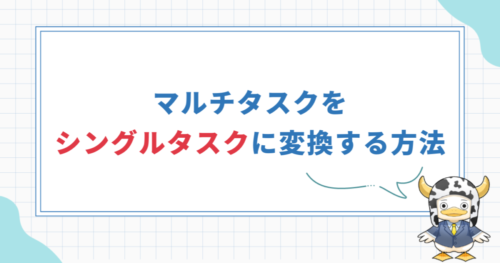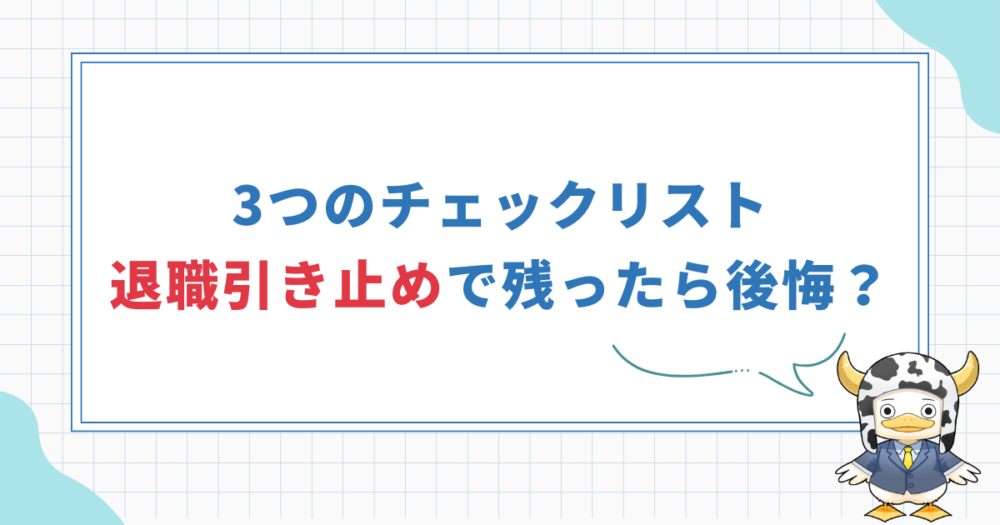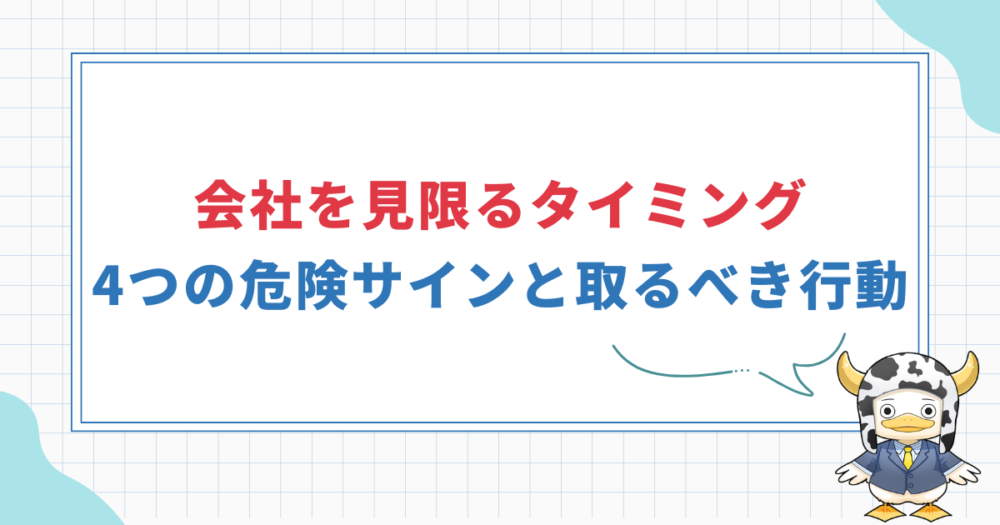「どうやったら定時に仕事を終わらせられるの?」



「イライラせずにどんどん仕事を進めたい!」
このように考えたことはありませんか?
特に、考えすぎてしまったり、他の人に仕事を頼めない繊細さんは、悩むことが多いのではないでしょうか?
この記事は、そんな悩みを解決できる内容になっています。



本記事を読んだら、焦りやイライラもなく、定時に仕事を終わらせることができるようになるでしょう!
記事前半では『仕事が終わらない人・仕事が早い人の特徴』『仕事が終わらない原因』を解説します。
そして記事後半では、仕事をスムーズに終わらせる『タスク手順書の作り方』や『集中できない人が簡単にできるポイント』を具体的に解説します。
仕事が進む・進まないの定義
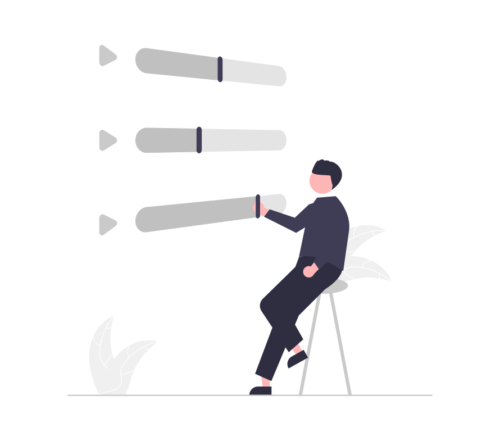
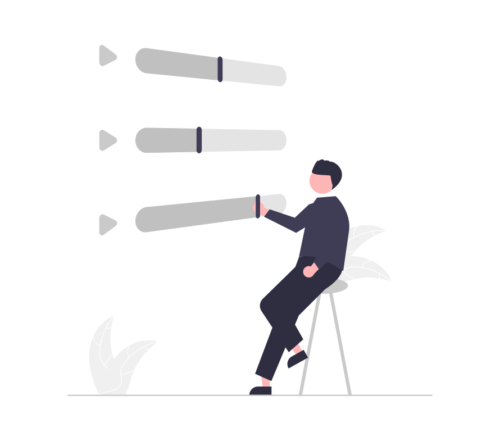
まずは、「仕事が進んでいる状態」と「仕事が進んでいない状態」を確認しましょう。
順に解説しますね!
「仕事が進んでいる状態」
タスクが終わっているということは、報告や成果物などの期限も守られている状態です。
また、仕事は複数のメンバーでおこなうため、コミュニケーションが取れている状態だと仕事が進んでいきます。



メンバーとコミュニケーションが取れると、仕事も進みやすいよ!
仕事が進んでいない状態
一方、仕事が進んでいない状態はどうでしょうか?
決まったタスクが終わっていないことを指します。
さらに言うと、必要なタスクすら決まっていない状態です。こんな状態だと、締め切りが守られることはありません!
職場のメンバーとの意思疎通も少なく、1人で仕事をこなさなければならない状態に陥っており、仕事のスピードも上がりません。



実行タスクが決まっていないと、期限に間に合わない!
仕事が終わらない人の特徴
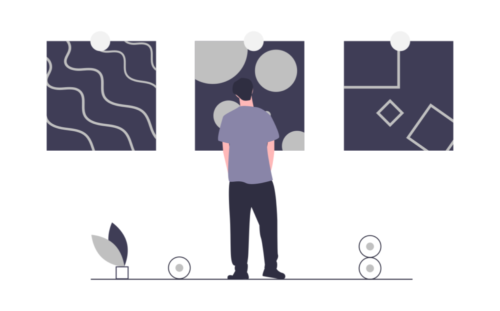
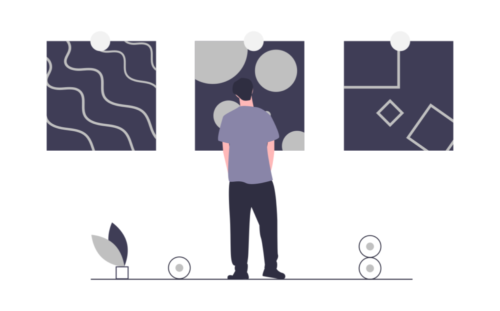
次に、仕事が終わらない人の特徴見ていきましょう。
以下に特徴を挙げます。順に解説しますね!
- 作業途中で中断することが多い
- 動き出しが遅い
- 1人で理解できるまで考える
作業途中で中断することが多い
仕事が終わらない人は、作業途中に止まっています。
単にリフレッシュなら良いのですが、「次に自分が何をすれば良いのか?」が分からないのです。



1回の中断は短くても、中断の回数が多いとこなせる仕事量は結果的に少なくなってしまう!
動き出しが遅い
仕事が始まっても、すぐに作業に移れないのが仕事が終わらない人の特徴です。
動き出せない理由は、「最初に何から始めれば良いのか?」が明らかになっていないからですね。



スタートが遅いと、仕事が終わる時間も当然遅くなってしまいますね…。
1人で理解できるまで考える
1人で考え抜く力は社会人として重要なことです!
ただし、それは答えが出せる場合に限った話です。



自分だけで答えの出せないことに力を注いでいる人も多いように感じます。
仕事が早く終わる人・生産性が高い人の特徴


一方、仕事が早く終わる人・生産性が高い人の特徴を確認しておきましょう。
以下に特徴を挙げます。順に解説しますね!
- 思考停止・作業停止している時間が短い
- 作業開始が早い
- 1人で考え込まない
思考停止・作業停止している時間が短い
まず、考える時間と作業する時間を分けています。
考える時は一切作業をせずに、やるべきタスクを考えて洗い出します。
タスクを列挙し終えたら、やっと作業に移ります!
タスクをすべて洗い出したため、作業中断が起こりません。



思考時間と作業時間を切り離して考えよう!
作業開始が早い
上述の通り、思考時間でタスクを洗い出しているため、1つ目のタスクを開始するまでの時間が非常に短くなります。
作業のスタートが早いため、仕事がどんどん終わっていきますよ!
一度作業が始まってしまえば、仕事のリズムにも乗りやすいですよね!



実行タスクを洗い出すと、作業開始のスタートが早い!
1人で考え込まない
仕事が早い人は、良い意味で自分だけでは考えません。
これは、「自分だけで答えが出せないのであれば、分かる人に聞くのが正解だ」という意味です。
「そんなんで人に頼って良いの?」と思うかもしれません。
しかし、みなさんも分からない単語があればネット検索をしますよね?
考えても答えが出せない仕事は、知識・スキルを持っている人に聞いた方が時間を無駄にしませんよ!



答えの出せない問いは、考えずに聞くのが正解!
仕事が終わらない原因


次は、「仕事が終わらない人」と「仕事が早く終わる人」の特徴から、仕事が終わらない原因を分析していきます。
以下のような原因があり、これらを1つずつ見ていきましょう。
- 実行タスクを洗い出せていない
- やること全体を考えすぎる
- 知識・スキル不足を今すぐ改善しようとする
実行タスクを洗い出せていない
前述の通り、仕事が終わらない人は「作業途中で中断することが多い」ということでした。
この理由は、「実行タスクを洗い出せていない」ことによるものです。



実行するべきタスクが出揃っていると、「次に自分が何をすれば良いのか?」という考える必要もありません!
例えば、「カレーを作ること」を考えてみてください!
簡単に以下のようなタスクリストが出てくると思います。
- 野菜を洗う
- 野菜、肉を切る
- 鍋を用意して火をつける
- 鍋に具材を入れて炒める
- 水を加えて煮たら、カレー粉を入れる
上記のように、いちいち止まることはありません。
レシピという手順があるからです。



この例のように、タスクを洗い出しておけば、料理に限らず仕事でも作業が止まることがありません。
やること全体を考えすぎる
仕事の多くは、5分程度の短い時間で終わるものではありません。
場合によっては、1時間以上〜何日も必要になることだってあります。
そうなると、「仕事が終わるイメージが湧かない!」いう気持ちになってしまいますよね。
ただ結果的に、仕事は複数の細かいタスクの積み重ねで、1つ1つのタスクは小さくて単純なため、時間が多くかからないんです。



複雑な仕事も単純で細かいタスクが絡み合っているだけ!
料理の手順のように、そのタスクを最初から順番にやっていくことに集中できると良いでしょう。
仕事の全体像を捉えるのはとても良いことですが、いざ行動する時は部分に集中するのがオススメです!
知識・スキル不足を今すぐ改善しようとする
仕事を終わらせたければ、知識・スキル不足を今すぐに改善しないでください!
誤解されそうなので、もう一度言いますね。
知識・スキル不足を「今すぐに」改善しないでください!
どんな仕事でも、知識やスキルをつけることは重要ですよね?
しかし、仕事をしている最中に改善をしてはいけません。
仕事というのは、すべて理解したり、完璧にこなしたりすることはできません。
自分の知識不足、スキル不足を理由にしていたら、いくら時間があっても仕事が終わりません。



仕事を完璧にこなそうと思わなくて問題ナシ!
仕事が進むことによるメリット


次に、仕事が進むことによるメリットについても理解しておきましょう!
メリットをまとめると以下の通りで、順に解説していきます。
- 1つ1つの仕事の質を高めることができる
- ストレスなく仕事を進めることができる
- 期限を守ることで信頼を勝ち取ることができる
1つ1つの仕事の質を高めることができる
例えば、ある仕事Aが計画以上に長引いた場合を考えます。
そうなると、他の仕事Bに注力する時間は減少してしまいますよね?
もしかすると、嫌々ながら残業をして仕事Bを終わらすのかもしれません。
仕事Aが他の仕事Bにも影響しているということ!
仕事が進むとは、やるべき複数のタスクが計画通りに終わっていることです。
今回の場合だと、仕事Bの質は下がりそうですよね。
計画通りにタスクが終わら巣ことができれば、1つ1つの仕事に時間をかけることができます。



時間をかけることができれば、自然と仕事の質は高まっていきますよね!
ストレスなく仕事を進めることができる
前提として、単純に仕事をこなすだけで心身にはストレスがかかります。
それなのに、さらに仕事が進んでいないとどうなりますか?
難しい仕事を短時間で完了することが必要になってきます。
短時間で仕事が終わらなければ、残業をしたり、休日出勤の可能性も出てきてしまいます。
そうなると、心身ともにストレスがかかってしまいます。



仕事をどんどん進める能力をつけると、みなさんの心身へのストレスを軽減できますよ!
期限を守ることで信頼を勝ち取ることができる
仕事が進むということは、成果物を期限内に早く提出できるということです。
その成果物の行き先は、上司であったり、他社のクライアントであったりします。
上司やクライアントは、期限内に成果物が手元に届くと安心します。
言い換えると、期限内に提出してくる人のことを信頼し、次の仕事を任せることができます。



期限内を守った仕事が信頼を勝ち取る!
イライラせず仕事をスムーズに終わらせるタスク手順書


ここからは、焦りやイライラのない『仕事をスムーズに終わらせるタスク手順書の作り方』を解説していきます。
タスク手順書の作り方は以下の通りで、順に解説していきます!
- やるべきタスクを書き出す
- タスクに名前をつける
- タスクを分解する
- 時系列順に並べる
- 誰がやるのかを色分けする
- 順番通りにやっていく
以下の記事でも詳しく書いているので、ぜひ読んでみてください。



タスク手順書を作成してから仕事をすることで、迷わずに仕事を進めることができます!
やるべきタスクを書き出す
まずは紙、PC、スマホのメモで、やるべきタスクを書き出します。
この時点ではメモ程度となるため、完璧に書き出さなくて大丈夫です!
タスクに名前をつける
次に、タスクに対して名前をつけます。
例えば、「新商品企画の会議資料の作成」などです。



名前をつけるだけで全体像がイメージしやすく、取りかかりやすくなるんです!
タスクを分解する
タスクに名前をつけることができたら、タスク分解をしていきます。
達成したいタスクを細かく分解するという意味ですね。
「会議の開催」を例に、要素的分解を使って解説をしていきます。
この場合、以下のようなことを具体的なタスクを実行する必要があります。
- 場所の予約
- 参加者の選出
- 参加者の日程調整
- 議題の決定
- 議決方法の決定
- 資料作成



一言に「会議の開催」と言っても、6つのやるべきタスクがありました。
時系列順に並べる
次は、出てきた要素を時系列順に並び替えます。
まとめると、以下の通りです。
- 参加者の選出
- 議題の決定
- 議決方法の決定
- 参加者の日程調整
- 場所の予約
- 資料作成
誰がやるのかを色分けする
次に自分がやることと、他者がやることを色分けしていきます。
上記の例で、自分が管理職でない一般社員の場合を考えます。
上記の(1)(3)は上司がやること、(4)(5)(6)は自分がやること、(2)は上司と自分がやるといった具合です。
これを色分けすると、以下のようになります。
- 議題の決定
- 参加者の選出
- 議決方法の決定
- 参加者の日程調整
- 場所の予約
- 資料作成
黒色は自分がやること、青色は上司がやること、緑色は誰かと一緒にやることです。



色を分けることで、自分が取り掛かることと相手に依頼することが明確になります。
順番通りにやっていく
ここまで完成したら、あとは順番通りにやるだけです。
今回の場合は、(1)議題の決定を上司に依頼することから始まります。
集中できない人が簡単にこなせるポイント
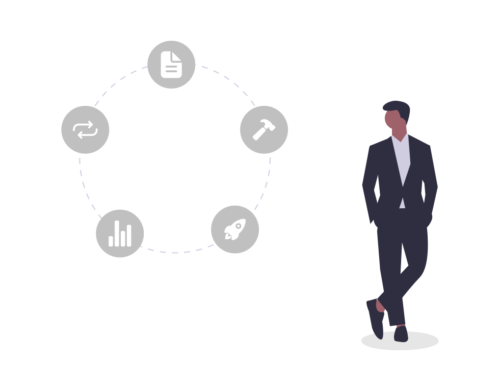
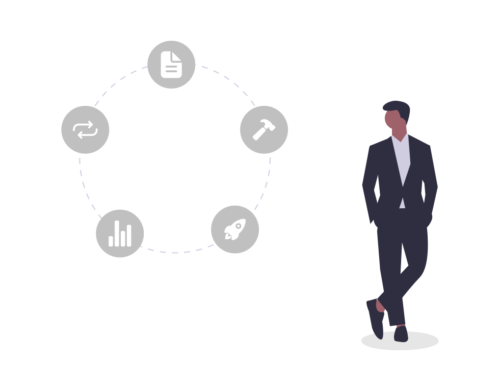
いざタスクに取り掛かろうとしても、集中できずに時間がかかってしまうことがあります。
そんな人のために、タスクを集中してこなす方法を解説します。
以下にポイントをまとめます。順に解説しますね!
- 手順書の1番目の項目を簡単に設定する
- 最初の手順だけに集中する
- 仕事に優先順位をつける
手順書の1番目の項目を簡単に設定する
タスク手順書を作成できたとしたら、もうタスクを終えたとほぼ同じです。
ただ、さらに仕事のスピードを上げたければ、タスク手順書の1番最初の手順を超簡単にすることをオススメします!
仕事の完了時間は初動で決まると言っても過言ではありません。



仕事は初動で決まるので、簡単に設定する!
タスク手順書の最初の手順を5分程度で終わる簡単なものにできれば、初動の完了時間が短縮できます。
上記の例では「議題の決定」で、上司に考えてもらうものになります。
したがって、上司に連絡をすれば良いだけです!



これさえ早く終わらせれば、あとは勝手に仕事を進めていきやすくなります。
最初の手順だけに集中する
タスク手順書を作ると、分解された細かいタスクがたくさん出てきます。
細かいタスクだと作業は明確になりますが、複数のタスクがあると圧倒される人もいますよね?
そういった場合には「1つ目だけに集中して完了させれば良いよ!」と念じましょう。
1つ目だけだと気が楽ですし、簡単に設定させているので作業は楽なはずです!



1つ目のタスクを終えると、自然と「2つ目以降もやろうかな?」という気持ちになってきますよ!
仕事に優先順位をつける
1日にこなす仕事もたくさんあり、「どれからやれば良いんだ!」と思うことがありますよね?
先ほどの例では、「会議の開催」という1つの仕事でしたが、実際1日には複数の仕事があります。
例えば、以下のような複数の仕事があります。
- 会議資料を準備すること
- お客様との日程調整をすること
- デスク整理をすること
- 会議の開催をすること
この中で優先順位が高いものから終わらせる必要があります。



その時に、優先度の高さ = 重要度 × 緊急度という考え方を用いてみましょう!
重要度は、「会社にとって利益をもたらす仕事か?」「なくなったら困る仕事か?」などを考えれば良いでしょう。
緊急度は、「今すぐ終わらせる必要があるか?」を考えるとOKです。
補足ですが、何となく思いついた仕事は重要ではなく、緊急でもないものが多いので注意!
タスク手順書に従うと得られる意外なメリット


タスク手順書を使うことで、焦り・イライラなく、仕事を早く終わらせることが可能です。
ただ、それ以外にも意外なメリットが2つあります!
順に解説しますね!
- 相談や依頼がしやすくなる
- 他の人に仕事を任せられる
相談や依頼がしやすくなる
他人に相談や依頼をするのが苦手な人がいると思います。
そんな時にタスク手順書に「広報課4名で会場準備」(自分は広報課で働いている)と書いてあったらどうでしょう?
「タスク手順書に書いてあるから、広報課に仲間に手伝ってもらうしかない」と言い訳チックに依頼ができます!



相談や依頼をするのが苦手な人は、他人への相談や依頼をタスク手順書に入れることを強くオススメしますよ!
他の人に仕事を任せられる
タスク手順書を作るのが面倒に感じる人もいるかもしれません。
ただし、繰り返し同じ仕事をやる場合にはとても役に立つものになります!
作ったタスク手順書を見れば、考える時間を最小限にして作業時間に移れますからね。



繰り返し仕事にはタスク手順書がオススメ!
そしてさらに良いことがあります!
他の人が見ても理解できるタスク手順書を1回作れたのなら、その仕事はもう他の人に任せることができるんです!
他の人に任せることができたら、自分は他の仕事を進めることができますよね!



同僚や部下からもタスク手順書のおかげで感謝され、自分も多くの仕事をこなせて、定時に帰ることが実現!
注意点


ここまで、『タスク手順書の作り方』や『集中できない人ができるポイント』について解説してきました。



タスク手順書・集中できない人のポイントは理解できたけど、何か注意することはあるの?
最後に、注意点を2つ示しておきます。
以下2点を守ることで、焦り・イライラを減らした状態で仕事に取り組めるでしょう。
順番に説明しますね!
- 手順を完璧に作らない
- 優先順位をつけるのに時間をかけない
手順を完璧に作らない
手順書を作る際に、要素を全部書き出せなかったり、時系列順では計画を立てられないことがあります。
その場合は、完璧にできなくとも、分解して出てきた要素をできる順番で実行していくだけで良いですよ!
不完全でもタスクを実行してみてから、後でその記録を残すことで、改良されたタスク手順書を作れます。



他の人にタスク手順書を使ってもらって、手順書の改善点を指摘してもらうのも良いでしょう!
優先順位をつけるのに時間をかけない
前述の通り、複数の仕事がある場合には、重要度×緊急度から考えた「優先順位の高いもの」から取り組もうと説明しました。
優先度の高さ = 重要度 × 緊急度
しかし、この優先順位をつけるのに30分以上も時間をかけていたら本末転倒です。
いずれにしても必要な仕事なのであれば、どんな順番で取り組んで良いですよ!
もしそれで終わらないのであれば、仕事量が多いかもしれないので上司に相談してみるのもアリでしょう!



アドバイスがあるとしたら、超緊急な仕事があった時だけ最初に実行するのがベストでしょう!
まとめ
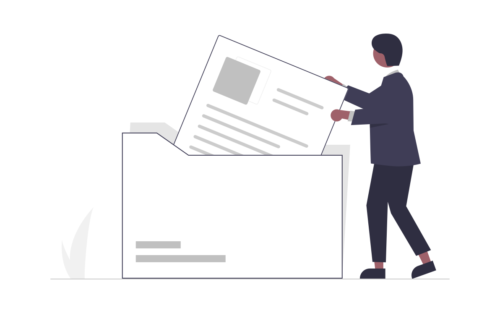
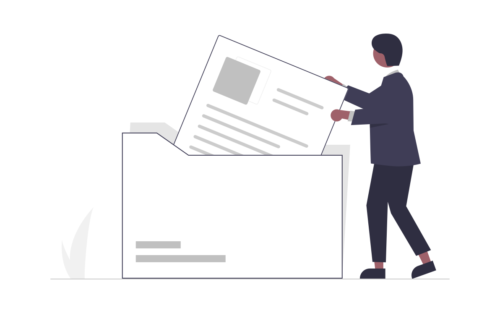
今回は記事前半で、『仕事が終わらない人の特徴』を確認したうえで『仕事が終わらない原因』を説明しました。
そして記事後半では、『仕事をスムーズに終わらせるタスク手順書の作り方』と『集中できない人が簡単にこなせるポイント』を解説してきました!
- 紙などを用意し、やるべきタスクを書き出す
- タスクに名前をつける
- タスクを分解する
- 時系列順に並べる
- 誰がやるのかを色分けする
- 順番通りにやっていく
- 手順書の1番目の項目を簡単に設定する
- 最初の手順だけに集中する
- 実行するタスクに優先順位をつける
まずは、タスク手順書の1つ目の項目を簡単に設定し、その項目の実行だけに集中してみましょう!
手順書の設定に慣れてきたら、他の人に仕事を振ってフィードバックをもらいましょう!
これができるようになると、以下のような変化があるでしょう!
- イライラや焦りがなく仕事を早く終わらせて、定時に帰ることがができる
- 人への依頼がしやすくなり、ストレスも減らすことができる
- ストレスが減るので、毎日の仕事で疲れにくくなる
今回の記事が参考になってくれることを願っています!