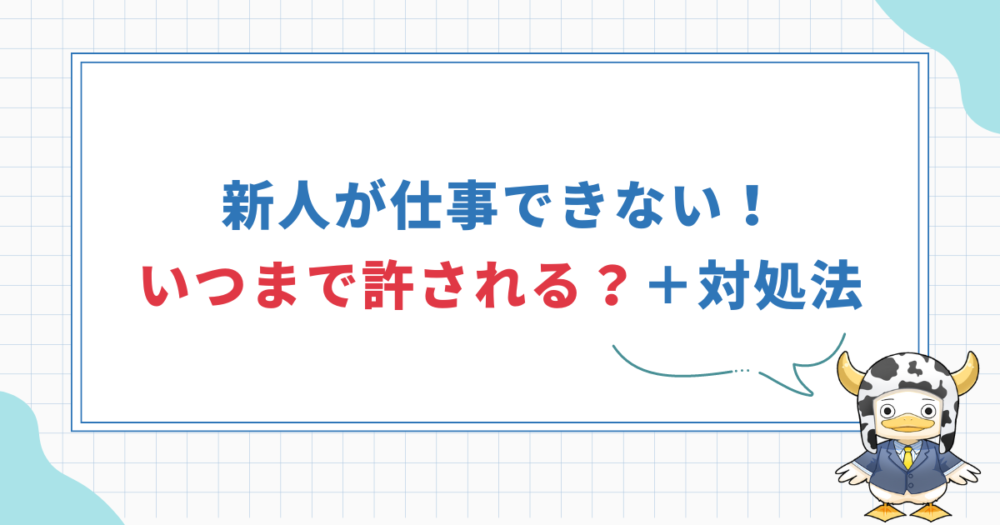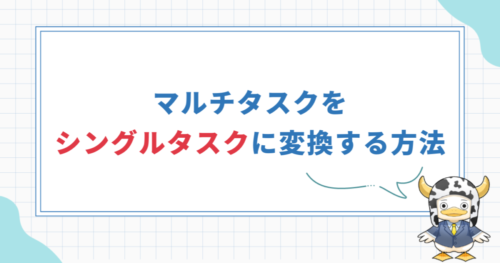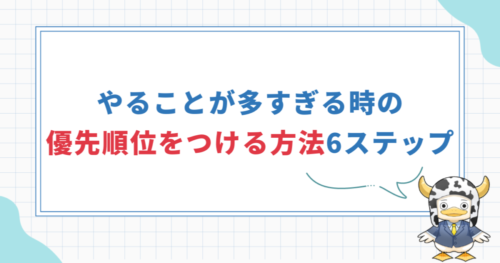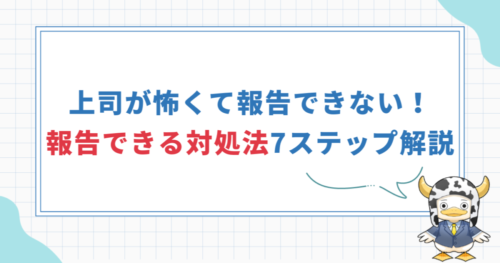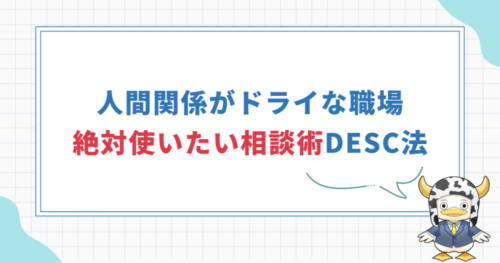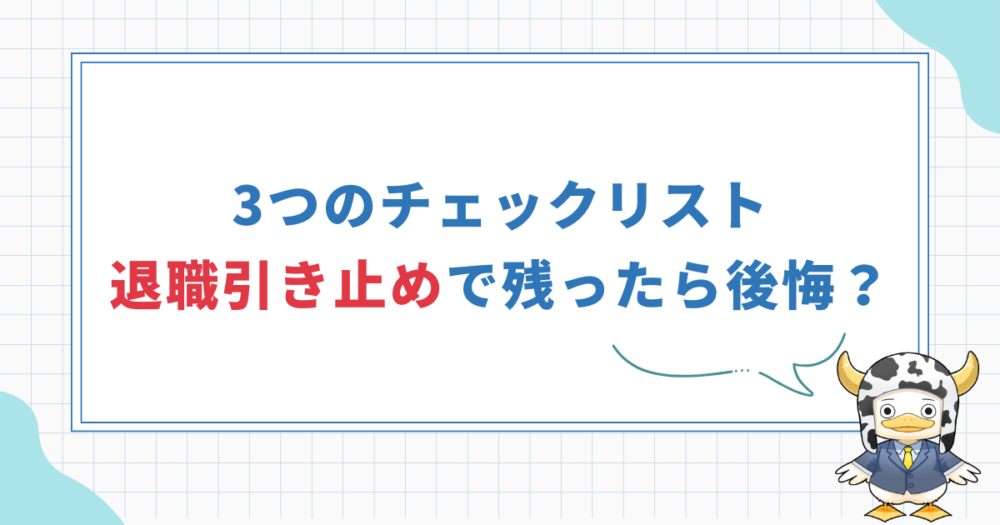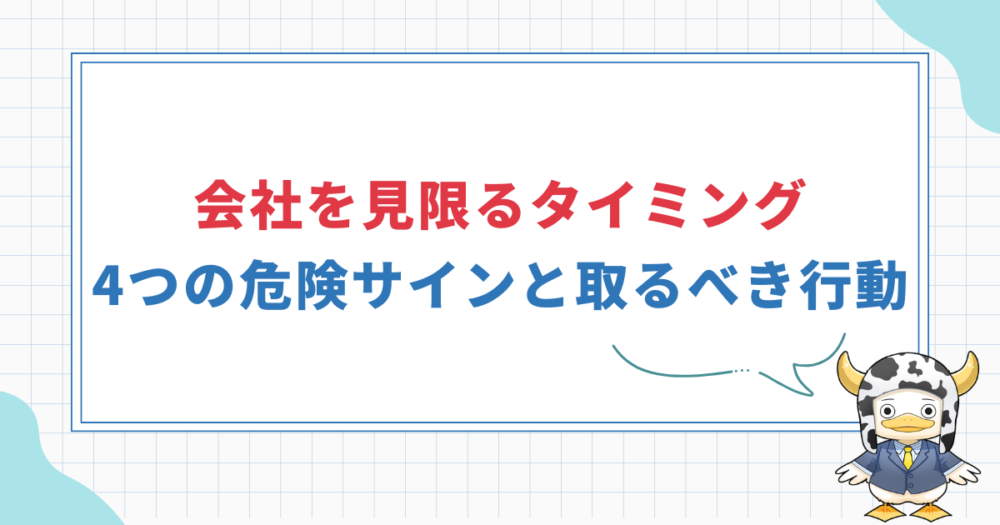「仕事ができないのはいつまで許されるの?」



「新人だけど、仕事ができるになりたい!」
このように考えたことはありませんか?
特に、関係ないことを考えて集中できない読者のみなさんは、悩むことが多いのではないでしょうか?
この記事は、そんな悩みを解決できる内容になっています。



本記事を読んだら、新人でもどんどん仕事を捌くことができるようになるでしょう!
どんなに小さな一歩であったとしても、自信を持って前に進むヒントを手に入れることができますよ。
少しでも前向きな気持ちで仕事に取り組めるようになれる内容となっています。
記事の前半では『仕事ができない新人の定義』や『仕事ができない新人のデメリット』を解説します。
そして記事の後半では『仕事ができるようになる対処法7ステップ』『仕事ができない新人への指導の注意点』を具体的に解説します。
仕事ができない新人の定義と前提


まずは、仕事ができない新人の特徴やミスが許される期間といった前提条件を解説します。
仕事ができない新人の特徴
仕事ができない新人というのは、任された仕事に時間がかかり、その成果物の質が低いということです。
ただ、そうなってしまうのも仕方なく、単純に経験が浅いためですよね。
また、仕事に入ってすぐは初めてのことが多く、仕事の進め方や専門ツールの使い方に慣れていないからです。



初めてやるスポーツを始めた時みたいな感じで、最初はなかなか上手にいかないことが多いですよね?
新人が仕事を覚える平均期間は?
「新人」として見られる期間は、一般的に1年程度でしょう。
始めの頃は失敗を繰り返しつつも、改善することで徐々に上達していきます。
仕事の種類やサイクル期間の長さにもよりますが、多くの人は新しい仕事に慣れるまで3〜6ヶ月ほどかかります。



僕は容量も悪いため、1年ほどかかりましたが…。
2年目からは若手社員としては見られますが、完全な新人とはみなされません。
1年の中で仕事にゆっくりと慣れていき、次のレベルに上がる準備をします。
新人のミスが許される期間
新人がミスをするのは当たり前のことですが、会社によって許される期間は異なりますね。
先述の通り、仕事に慣れるまで約3〜6ヶ月はかかるため、この期間がミスがある程度許容されるところでしょう。



ただ、長期的な研修期間が設けられている大企業などでは、さらに長く1年〜3年スパンになるかもしれません。
仕事ができない新人のデメリット


ここからは、仕事ができない新人のデメリットを3つ紹介していきます。
仕事を上手に進める能力を習得していないと、悪影響が出てしまいますね。
ミスによるやり直しが増える
新人は初めての仕事も多く慣れていないため、ミスが多くなりがちですよね。
1つの仕事を完遂するためにも、たくさんのタスクが存在しており、同時に学ぶ必要があります。
多くのタスクでミスを繰り返してしまうと、やり直しが増えて労力も倍増していくんです。



新人の時には、コピー機を使うだけでもかなり時間を取られることもある!
スケジュール管理ができずパンクする
新人はスケジュール管理に悩まされることもあります。
仕事の中には、重要なものとあまり重要でないものがあります。
仕事の全体像が理解できないままだと、重要度の異なる複数の仕事を進めるのが難しいでしょう。
例えば、仕事Aはいつまでに、仕事Bはいつまでに終わらせるべきか、正しく認識するのは困難です!



スケジュール管理ができていないと、仕事の山で頭がパンク状態になり重要なものを後回しにしてしまうことも!
価値のあるフィードバックをもらえない
新人の中には、上司や同僚からのフィードバックを受け入れられない人もたまにいらっしゃいます。
自分のやり方に自信を持ち過ぎていたり、失敗を指摘されることを嫌がるためです。
「ここを改善したほうが良いよ」と意見をもらっても、自分を変えないといった状態です。
自分に自信を持つのは良いのですが、自分にない視点で成長できるチャンスを失ってしまっています。



相手からの信頼も減り、アドバイスをもらえなくなっていく!
新人の仕事ができない理由


ではなぜ、新人は仕事ができないのでしょうか?
新人の仕事ができない理由について、3つ挙げていきます。
基本的ビジネススキルの不足
新人が仕事をうまくできない理由の一つは、基本的ビジネススキルの不足が挙げられます。
サッカーを始めたばかりの時に、ボールをコントロールできないのと同じ状態ですね。
地味な行動に見えるのですが、仕事ができない人は、以下2つのことができていません。
ゴールを設定しない
マラソンにはゴールが決まっており、それに向かって走り出しますよね?
仕事にもゴールの形が決まっていて、それががないままではどこに走っていいのかが不明瞭です。



何か仕事を頼まれた時に、どんな成果物(=ゴール)が求められているのか確認していないと仕事が進みません。
タスク分解ができない
仕事のゴールが決まると、そのためのタスクが複数出てくるはずです。
例えば、会議の資料作成をするにしても以下のようなタスクが出てきます。
- 会議の目的を明確にする
- アジェンダの作成
- プレゼン資料の構成を考える
- 資料に必要な情報収集
- 資料や文書の具体案作成
- 資料のデザイン
- 資料の校正・チェック



「なんとなく資料を作ればいいんだ」という認識だと、やり直しが増えてしまいますね。
研修や教育の不足
必要な研修や教育を受けていない場合にも仕事を上手に進めることは困難となるでしょう。
この理由については、新人側というよりも会社側の問題にも関係します。
会社が新入社員に十分なトレーニングを提供しないと、仕事の正しい進め方が分からなくなってしまいます。



ただし、新人側も受け身の姿勢は好ましくない!仕事を上手に進められないと、自分がストレスを溜め過ぎてしまう!
職場でのコミュニケーション問題
職場でコミュニケーションが円滑にできないと、新人は困ってしまいます。
仕事を自分だけでこなすことはできないため、分からない部分は聴く必要があります。
特に、上司とよく話し合わなければ、仕事の進め方を覚えられなくなるでしょう。



教わる立場ではないかもですが、同僚と情報共有ができるように相談なども必要!
仕事ができる新人になる対処法7ステップ


ここまで、新人の仕事ができない理由を確認してきました。
ここからは、仕事ができる新人になる対処法を7ステップで解説していきます。
仕事ができる人を真似する
仕事ができるようになるには、仕事を上手に進めている人の真似がやはり一番早いです!
専門的知識を除いて、仕事が上手な人は以下の2つができています。
タスク手順書を作る
まずは、やるべきタスクを洗い出すことが大切です。そのために①ゴール設定と②タスク分解をしていきます!
ゴール設定をする
最終成果物のイメージは最初に作っておきます。
仕事を任された時に相手が何を求めているのかを明確にしておくという意味です。
会議の資料と言われても、①プレゼン資料なのか、②文書で箇条書き程度でいいのか、といった具合です。



これをやっておくがだけで、仕事の見通しがつきますよ!
タスク分解をする
最終ゴールを設定できたら、そのためのタスク分解をします。
分解をしていかないと、何から始めるか迷ってしまうんですよね。
簡単ですが「会議の開催」を例に、要素的分解を使って説明しますね。
会議の開催をする場合、以下のようなことを考える必要があります。
- 議題の決定
- 参加者の選出
- 議決方法の決定
- 参加者の日程調整
- 場所の予約
- 資料作成
優先順位をつける
優先順位をつけずに仕事を進めると、取り組むべきことが分からずに、重要度の高い仕事を後回しにしてしまいます。
そうなると、重要度の高い仕事の時間が後で必要となり、残業が増えてしまうんですよね。
やるべき仕事を見極めるため、重要度×緊急度マトリクスを用いたフレームワークをやってみることをオススメします!
重要度:「仕事の価値がどれだけあるのか」を示す指標
緊急度:「仕事への対応の早さがどれだけ求められるか」を示す指標



緊急度は低いけど重要度が高い仕事をこなせるようになっていき、成果も出せるようになることを目指します!
積極的かつ有用な質問をする
新人の時には、分からないことがたくさん出てくるため、積極的に質問をすることが大切です。
ただし、質問のやり方は考えないといけません。
質問をする際には、以下の事項を満たせると良いでしょう。
- 事実ベースの状況報告
- 自分が実践した方策
- 自分が相手に何を求めているのか
上記の観点について、失敗例と成功例を見ていきましょう!
質問の失敗例



「上手くいく営業の方法を教えてくれませんか?」
質問の成功例



「今、〇〇社の方に、会社の商品Aの紹介をおこなっています。
他社との価格や機能の比較をし、優位性があることを説明しました。
しかし、なかなか商品を購入検討してもらえません。
価格や機能の説明以外に何か検討してもらいやすくなる項目はありますか?」



積極的な質問は大切ですが、自分で考える部分、相手が答えやすくなる準備は必要となるでしょう!
業務外で自己投資をする
業務外での自己投資が必要と言われると、嫌がる人は多いでしょう。
ポイントとなるのは、仕事とは独立して考えることです!
業務時間外に身につけた知識やスキルを仕事と掛け算するイメージですね!



僕だったら、このブログ自体が本業の文書作成能力に応用できていると思います!
みなさんも、プライベートでやっている活動が仕事にも活かせるかもしれませんよ!
SNSを見る時間なども情報を得ているかもしれませんが、ついでに仕事にも使えたら一石二鳥かもですね!
職場での継続的なコミュニケーション
仕事をスムーズに実行するためには、先輩や上司などと継続的にコミュニケーションを取ると良いでしょう。
そのために以下の2つの方法をオススメします。
効果的に報告する
先輩や上司への報告で、気を遣ってしまうことありませんか?
そんな時、以下の7ステップで報告してみてください!
- 報告するメリットを確認する
- 報告内容を整理する
- 提案する場合は選択肢を用意する
- 報告のタイミングを考える
- 報告の方法を使い分ける
- 結論から簡潔に説明する
- 自分なりの考えを話す
具体的かつ正確に報告できると、自分の頭も整理できますよ。
さらに、報告相手からアドバイスをもらえることだってありあす!
詳しいやり方は、以下の記事をご覧ください!
DESC法で相談する
相談を難しいと感じている人は多いでしょう。
事前に相談内容を整理して、伝える時のことをシミュレーションしておくと安心できます。
そんな時、相談の準備方法として「DESC法」をオススメします。
このDESC法は、相手の状況を考慮しつつも、自分の状況を具体的に伝え、良い方向に向かうための相談法のことです。
DESC法は、以下の4つの項目から構成され、英語の頭文字をとったものです。
- Describe:描写する
- Express:説明する
- Specify:提案する
- Choose:選択する
詳しいやり方は、以下の記事をご覧ください!
実行の進捗モニタリング
目標を設定するまではできたけど、その進捗をモニタリングしていない人は多いです。
仕事ができるようになるには、設定した目標に対して実行し、その進捗を確認することが必要となります。
タスク手順書を作成した時、分解されたタスクが複数出てきましたよね?
この細切れにされたタスクの「完了予定日」と「実際の完了日」を書いていくと良いですよ!
会議の開催をする場合、以下のようなことを考える必要があります。
- 議題の決定
- 参加者の選出
- 議決方法の決定
- 参加者の日程調整
- 場所の予約
- 資料作成



自分の仕事のペースを把握しながら、遅れていたら相談をするのです!
業務の振り返り
毎日、仕事の振り返りを実施することで、何ができるようになったのか、何を改善するべきなのかを把握することも大切です!
できるようになったことを確認することで、自分の自信にもつながっていきますよ!
改善すべき点については、次の取るべき行動も一緒に書き留めておくと、いちいち悩まずに動き出すことができますよ!



自分だけのマニュアルを作っていくイメージですかね!
フィードバックを受け入れる
他者からのフィードバックは、自分の仕事を改善するために非常に有用となります。
自分を客観的に見る人はいますが、主観を完全に排除することは不可能です。
人からもらったフィードバックは一度吟味して受け入れ、必要か不要かの判断をしましょう!



「あのフィードバック、やっぱり試せば良かったかな〜」とならないように、フラットに検討することが大切!
よくある質問・補足情報


補足情報としてよくある質問に答えます!
新人が転職を考えるタイミングはいつが最適か?
上記のような行動をしても、上手にできない、職場になじめないのであれば転職を考える必要も出てきます。
新人が転職を考えるタイミングとして、最低6ヶ月〜1年はその会社で働いてみた後が妥当と考えます。
この期間は働いてみないと、仕事に慣れたり、その会社の全体像を理解したりはできないでしょう。



明らかに、パワハラや違法な残業の強要などがあれば、例外で6ヶ月未満での退職も検討しよう!
転職エージェントを利用した転職活動を考えている人には「転職・求人・人材紹介のJAC Recruitment(JAC リクルートメント)」をオススメしています!
仕事ができない新人への指導上の注意点


ここまで、『仕事ができる新人になる対処法』を7ステップで解説してきました。



方法があるのは分かったけど、指導する側としての注意点はあるの?
実際に指導側に回った時のことも考えてみましょう。
以下の注意点2つを守ることで、新人を育てる時のことも考えることができるでしょう!
感情任せに指導しない
新人への指導の際には、感情的に指摘することは避けるべきです。
怒っていると、指摘内容よりも感情によるイメージが伝わってしまいます。
サッカーやテニスを例にしても、試合でミスをした選手に怒ったように助言をしても伝わらないですよね?



感情的に伝えるのでなく、冷静にアドバイスをすることで、新人は報告や相談をしてくれる!
フィードバックの欠如を避ける
新人が伸び伸びと成長するためには、フィードバックが必要不可欠となります。
定期的なフィードバックがなければ、新人にとっては何が正しくて、どこを改善しなくちゃいけないのか分からなくなりますよね。
車の運転中で、現在地もナビゲーションもないようなものです。



フィードバックと言っても、僕は常に具体的で正しい方向への助言はいらないと考えます!
以下のような声かけだけでも十分です。
- 「頑張っている行動を見てるよ」
- 「良い感じにできてるよ」
まとめ
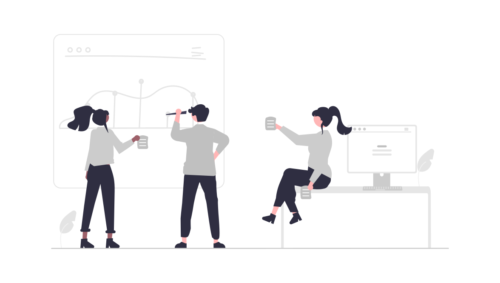
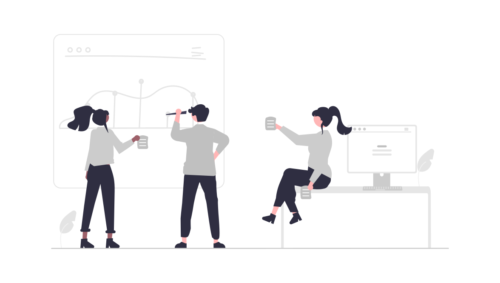
今回は記事前半で、『仕事ができない新人の定義』を確認したうえで『仕事ができない新人のデメリット』を説明しました。
そして記事後半では、『仕事ができるようになる対処法7ステップ』『仕事ができない新人への指導の注意点』を解説してきました!
新人の方が直面する「できない」状態は、誰でも起こる現象です。
しかし、そのまま放置していても成長することはできません。
経験を積むことに加えて、積極的に質問をし、フィードバックを受け入れ、業務外での自己投資をすることが重要です。
さらに、職場内でコミュニケーションを通したアドバイスを受け、進捗モニタリングをすることで、成長を感じられるようになるはずです!



失敗を恐れずに、挑戦する姿勢を持ち続けることが、新人から一歩進むための大切なカギとなります。
自分を信じ、勇気を持って前進していきましょうね!
この行動ができると、以下のような変化があるでしょう!
- どんな状況でも冷静に解決策を見つけられ、様々な仕事を適切に処理できる
- 上司や同僚と建設的な議論ができ、協力して成果を得ることができる
- 自分の成長を計画的に管理し、自分をさらに高められる
対処法を講じでもダメなら、転職という選択肢もあります!
転職エージェントを利用した転職活動を考えている人には「転職・求人・人材紹介のJAC Recruitment(JAC リクルートメント)」をオススメしています!
今回の記事が参考になってくれることを心から願っています!